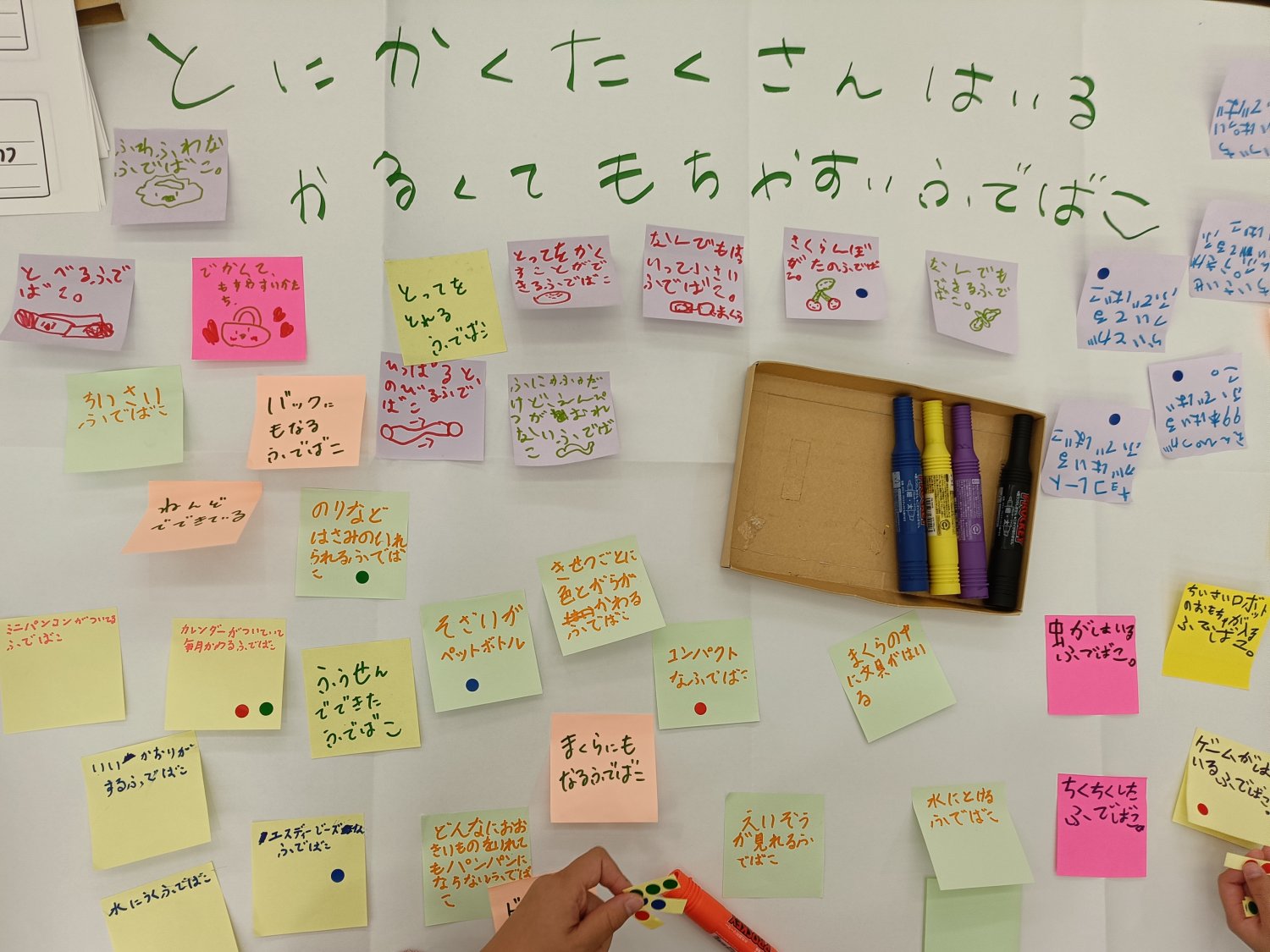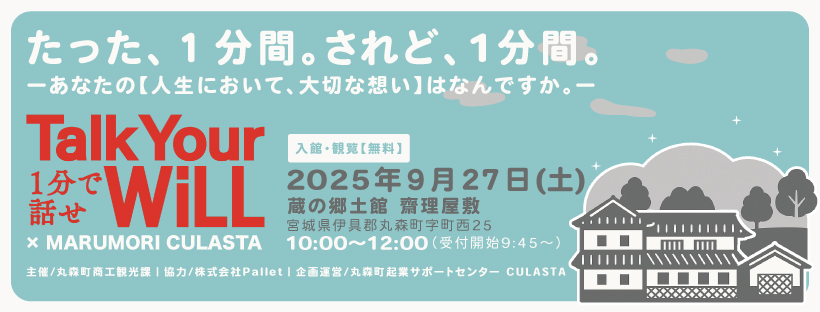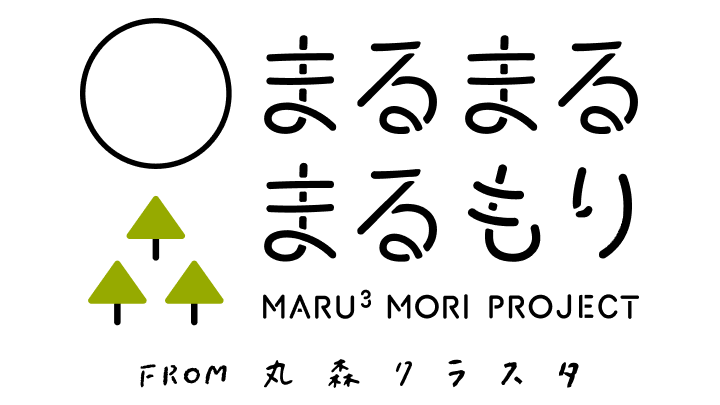まるもり仕事図鑑では、町の資源やカルチャーに光を当て、ビジネスの種となり得る魅力をご紹介していきます。
今回ご紹介するのは、丸森町の冬を象徴する「干し柿」。地域に根付いた冬仕事として行われてきた干し柿づくりと、その継承に取り組む若手農家の取り組みを伺いました。
【お話を聞いた方】
鈴木舞香さん
宮城県丸森町で干し柿づくりに取り組む若手農家。青年海外協力隊としてアフリカ・ザンビアで活動した経験から、「地域に根ざした仕事を自分の手で生み出したい」と感じ、地域おこし協力隊を経て就農。現在は地域のベテランたちに学びながら、干し柿づくりに挑戦している。

秋が深まるころ、丸森町のあちこちに、橙色の柿が実ります。
干し柿づくりは、この町の冬仕事のひとつです。
干し柿は、寒暖差が大きく、風通しのよい土地が向いているとされ、丸森町の気候風土は、それにちょうど適しています。秋にはボランティアの方々も訪れ、一斉に柿剥きが行われます。特に耕野地区での受け入れは、2週間で200人にも上るそうで、毎年のように訪れるのを楽しみにしてくれているリピーターの方も多くいるといいます。
地域の“へた回し”の名人も、この時期に活躍します。へた回しというのは、柿を吊るす前に、枝の“へた”の部分をくるりと回して二股に整える作業のこと。紐をかけやすくするための下準備で、柿づくりの中でも手の感覚がものを言う作業です。地域にはこの“へた回し”の名人がいて、手際よく何百個も回していく姿は、まさに冬の風物詩です。
そんな地域の干し柿づくりを次の世代につなげようと、若手農家・鈴木舞香さんが活動しています。
地域に残る仕事を受け継ぐ
かつて海外での協力活動に携わっていた舞香さんは、現地で「働くこと」「生きること」の意味を改めて考える経験をしました。ザンビアでは、地方を離れて都市に出た若者が仕事を得られず苦しむ姿を目にしました。一方で、地域に残り農業に取り組む人たちは、学校を出ていなくても自分の手と頭で仕事を生み、暮らしを立てていました。
それを見て、「日本も地方から人が離れていくのは同じ。でも、やり方次第で地域に仕事を生み出すことはできる——そう思ったんです。」
丸森町では地域おこし協力隊として3年間の活動を経て、この町で就農することを決意。数ある作物の中で干し柿を選んだのは、地域の方々の思い入れと、後継者不足の現状に心を動かされたからでした。「干し柿は丸森の誇る産品ですが、生産者はほとんど70代。燃料費や輸送費の高騰もあり、続けるのが難しくなっている方も多いんです。誰かがやらなければ終わってしまう、そう感じて始めました。」
研修期間中は地域の方の“かきばせ(干し場)”を借り、機械や道具を共同で使いながら、皮のむき方から燻蒸のタイミングまで、すべてを学びました。
「干し柿は風を当てなければいけないけれど、乾かしすぎてもカチカチになる。天候を読みながら、長年の感覚で判断していくんです。」
今年は新しい干し場を借り、自分ひとりでの挑戦が始まっています。
農業+αという関わり方
「収入を得るにはもっと広い土地が必要です。とはいえ、今すぐ空いている畑があるわけでもない。機械を導入するにも資金がかかります。農業一本でやっていくのは簡単ではないと感じます。」
それでも舞香さんは、悲観的ではありません。
「無理に“専業”を目指すよりも、農業を軸にしながら他の活動と組み合わせていく“複業”の形もありだと思っています。それに海外の農業に関わる時間をいつか持てたらとも考えています。」
自然と向き合う農業を目指して
もう一つの課題は、農薬との付き合い方です。
「指導を受けた時に“消毒は絶対”と言われたのですが、薬を撒いている自分の姿に違和感があって…。消費者も気にする人が増えていますし、本当は使わずに育てられたらと思っています。」
今年は試しに消毒を減らしたところ、思うような結果にはならなかったといいます。
「何もしないで減らすだけではだめなんだと分かりました。土から変えていかないといけない。簡単ではないけれど、理想に近づける方法を探っていきたいです。」

人が集う農のかたちへ
丸森町では少しずつ若い就農者も増えています。
「人手が足りない農家は多いけれど、通年で雇うのは難しい。だから、農業に関わりたい人と手が欲しい農家をつなぐ仕組みができたらいいなと思います。干し柿のボランティアに来る人も、みんな別の仕事を持ちながら、“関わりしろ”を求めて来てくれているんです。」
理想と現実の間で揺れながらも、地域に根を張って奮闘する舞香さん。
干し柿づくりは、長年支えてきた人々と新しい担い手の手によって、これからも丸森の冬に温かな彩りを添えていく。
<文>山下久美
<写真>佐藤浩子