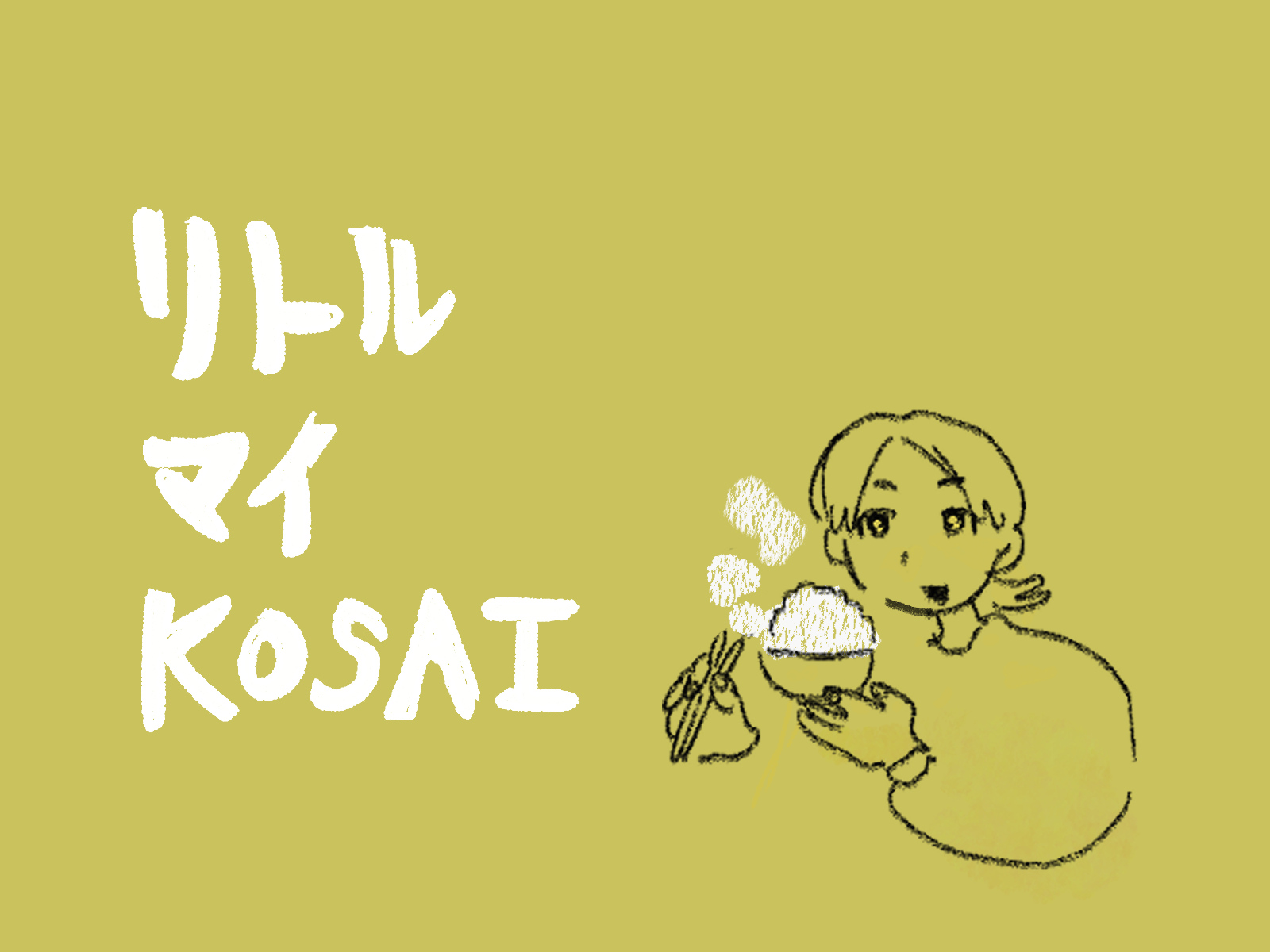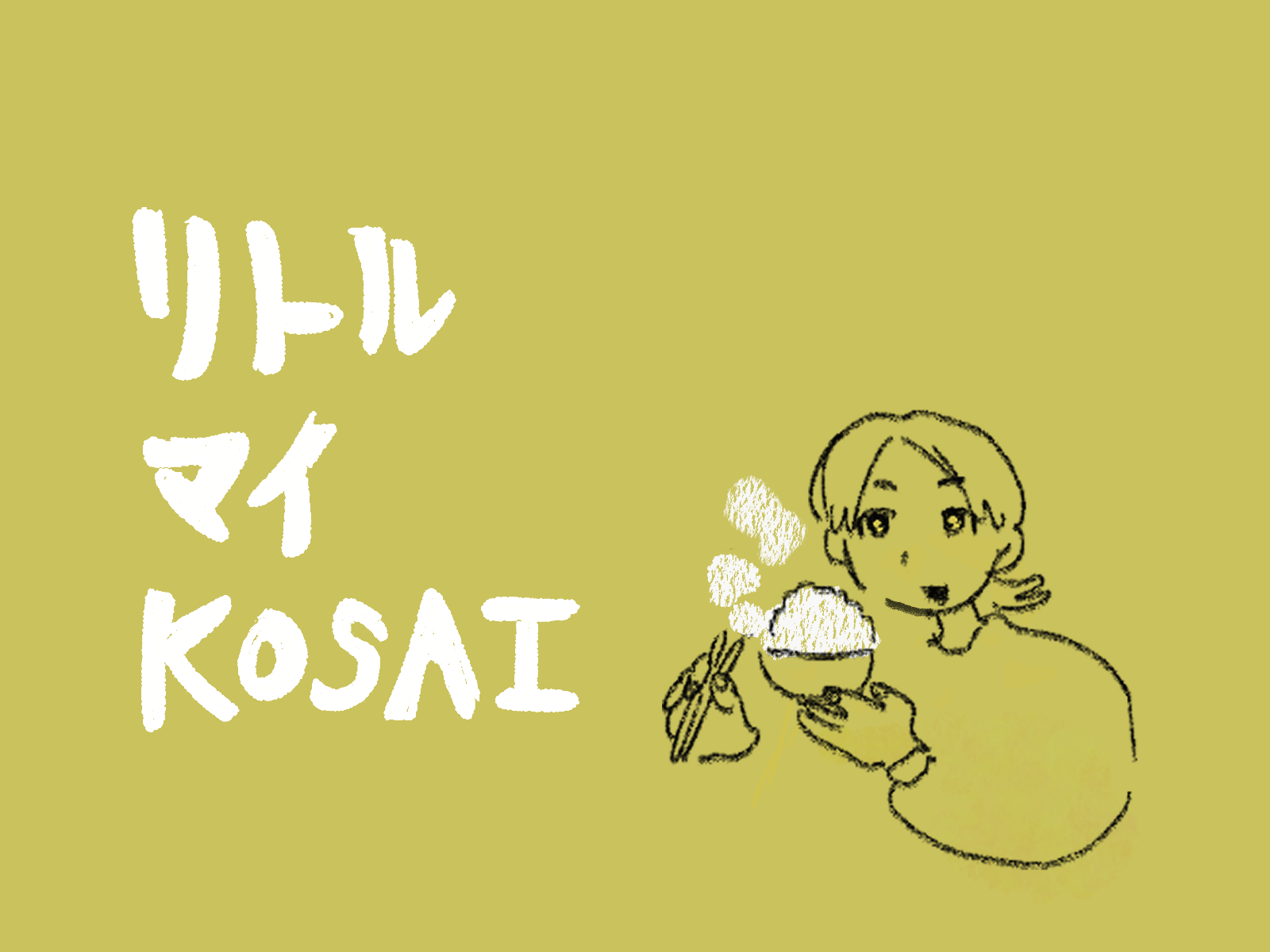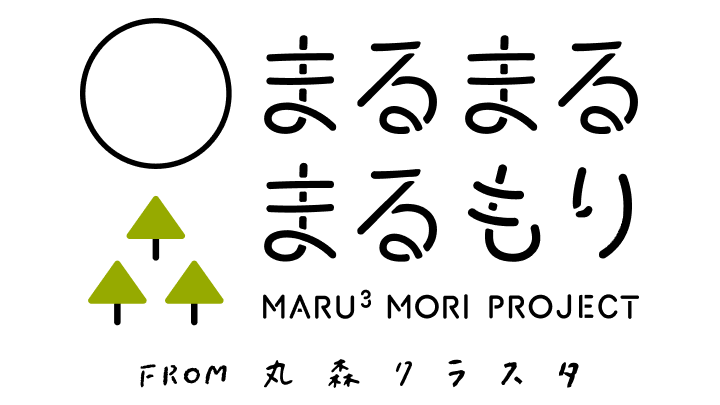まるもり仕事図鑑では、町の資源やカルチャーに光を当て、ビジネスの種となり得る魅力をご紹介していきます。
今回ご紹介するのは、「日本の棚田百選」にも選ばれた丸森町の大張沢尻の棚田。地域資源としての価値はもちろん、次世代につなぐ取り組みや、新たな活用の可能性について伺いました。
【お話を聴いた方】
大張沢尻の棚田を守り隊
岡崎匡人さん
丸森町役場農林課に在籍中、棚田に関わったことをきっかけに、個人としても保全活動に参加。2024年からは「大張沢尻棚田を守り隊」として、草刈りなどの維持作業に加え、「宮城ライシーレディ」の招致など広報活動にも力を注いでいる。

江戸時代から続く棚田の風景
丸森町の山間部では、今も多くの棚田を見ることができます。その中でも特に知られているのが、大張地区にある「沢尻の棚田」。1999年に農林水産省の「日本の棚田百選」にも選ばれ、地域の象徴的な風景として大切にされています。入口に設置された案内板によると、沢尻の棚田は江戸時代に開かれたとされています。年代の詳細は不明ですが、少なくとも150年以上にわたりこの場所で稲作が行われてきました。現在は大槻光一さん、佐藤忠吾さん、佐藤尚一さんの3人が「大張沢尻棚田集落協定」を結成し、作付けや管理を行っています。
支える人々の想い
棚田百選に選ばれた当初は、町内外から年間2,000人近くが訪れ、ボランティアとしての保全活動に加え、農業体験や見学など、さまざまな形で棚田と関わっていました。しかし時間の経過とともに関心は薄れ、担い手の減少や高齢化が深刻化。一時は「耕作をやめて維持管理だけにしようか」という声も上がりました。そんな中で、当時「大張まちづくりセンター」の事務局長を務めていた大槻光一さんが、生産者として加わることを決意。代々この棚田を耕してきた農家・佐藤忠吾さんも、「一緒にやってくれる人がいるなら続けられる」と感じたといいます。そして、保全会のメンバーとして支えていた佐藤尚一さんも賛同し、力を合わせることになりました。異なる立場の3人が思いを一つにしたことが、稲作が途切れることなく続いている今につながっています。
棚田の営みを広げていくには、現場の維持とあわせて、その魅力を「伝えること」も欠かせません。今回お話を伺った岡崎匡人さんも、そうした役割を担うひとりです。農地保全の補助金業務で棚田に関わったことをきっかけに関心を持ち、現在はボランティアとして、草刈りの手伝いをはじめ、SNSでの情報発信やテレビ局への取材依頼など、さまざまなかたちで棚田の魅力を伝え続けています。
活動を行う理由について、岡崎さんはこう語ります。「子どもの頃、親に連れられて何度か訪れたはずなのに、記憶にはほとんど残っていませんでした。でも、大人になって改めて棚田を目にしたとき、ただ純粋に“きれいだな”と感じたんです。そんな風景を守るため努力している人たちの姿を見ているうちに、棚田への思い入れが強くなり、保全活動に関わるようになりました。」
こうした個人の思いが重なり合うことで、棚田は守られ、活かされ続けています。
教育、環境、防災──多面的な価値
沢尻の棚田は、稲作だけでなく、地域にさまざまな恩恵をもたらしています。たとえば、伊具高校の農業系列の生徒たちは、5月から10月にかけて毎月この棚田で体験実習を行い、地域に根ざした農業を学んでいます。丸森小学校の5年生も、田植えや稲刈りの体験を通して、地域への愛着を育んでいます。
さらに、棚田は災害への備えとしても重要です。雨をため込みながらゆっくりと地中に染みこませる構造は、大雨時の土砂崩れ防止にも一役買っています。また、2023・2024年度に行われた調査では、沢尻の棚田は町内でも特に水生生物の種類が豊富で、貴重な生態系が今も息づいていることがわかりました。

棚田を未来につなぐには──「保全」から「活用」へ
現在、稲作を担う農家の全員が70代。今後の後継者不在は避けて通れない課題です。しかし岡崎さんたちは、棚田を「農業だけで守る」のではなく、「多様な関わり方ができる場所」として活用する道も模索しています。いま、少しずつではありますが、こんな活用の可能性が模索され始めています。
■新たな関わり方の提案
「草刈りだけでも手伝いたい」「農業体験がしたい」「棚田で写真を撮ってみたい」──そんな想いに応える柔軟な仕組みづくり
■観光やイベントとの連携
農閑期のライトアップ、音楽イベント、キャンプ活用など、観光や文化と棚田を結びつける取り組み
■休耕地の活用
米づくりをしていない田んぼをビオトープとして整備し、自然観察や体験型プログラムを行う構想
■棚田米のブランド化
小分け販売や、町内の飲食店で棚田米を使うなど、魅力を高める試み
現在はアイデアを練っている段階ですが、今後の実現に向けた土台となっています。
先にも出てきた棚田の案内板には、最後にこんな決意が記されています。
「私たちは、沢尻の棚田の環境に対する重要性と歴史を理解し、後世に伝えていかなければならない。」
棚田で稲作を続ける人、その営みを支える人、魅力を伝えようと動き出す人──関わり方はさまざまですが、「未来へつなぐ」という思いが少しずつ広がっています。
地域にとって大切なものを、どう残し、どう活かしていくか。その問いに向き合う中で、新しい仕事のかたちが見えてくるのかもしれません。
<文> 山下久美